地域内外から52名が登壇、東三河から全国へ食・農の新たな可能性を発信
サーラ不動産株式会社(本社:愛知県豊橋市)は、2025年9月19日(金)・20日(土)に、全国の「食と農」のキーパーソンが東三河地域に集結するイベント「東三河FOOD DAYS 2025」を開催しました。

イベントの舞台である東三河地域は、愛知県の東部に位置し、中核市の豊橋市をはじめとする8つの市町村で構成され、豊川用水や恵まれた日照時間等の恩恵により、1,500億円余りの農業産出額を誇る、全国有数の農業地帯です。
本イベントでは、日本全国から212名の食・農分野のキーパーソンが集結し、多岐にわたるコンテンツが提供されました。
この記事では開催の背景から各コンテンツの様子をご紹介します。
開催背景
サーラ不動産は、地域の様々なプレイヤーと連携し、「農・食を軸とした地域の活性化」を目的とする「東三河フードバレー構想」を推進しています。
この構想のもと、東三河を「フードクリエイターの聖地」とするべく、次世代を担う人材の発掘と育成に注力しています。
その取り組みの一環として、地域内外の食・農にまつわるプレイヤーやコンテンツを集約し、交流と連携を深める場として「東三河FOOD DAYS 2025」を開催しました。
このイベントは、参加者が共に語らい、繋がり、東三河の食・農の魅力をより多くの人に広めることを目指しています。
各コンテンツ紹介
「東三河FOOD DAYS 2025」は、DAY1(9月19日)とDAY2(9月20日)の2日間で開催され、合計6つのコンテンツを実施しました。
様々なクロス(掛け算)を生み出すことをテーマに、多様なプレイヤーや事業の掛け合わせを感じさせる2日間となりました。
DAY1
①「OPENING TALK」
株式会社UnlocXの田中宏隆氏による地域発のフードイノベーションの今度の可能性が語られました。今回のトークでは、最先端のフードテックから、地域ならではの資源を活かした新たな食の創造、そしてそれが地域にもたらす変革について、多角的な視点から掘り下げていきました。

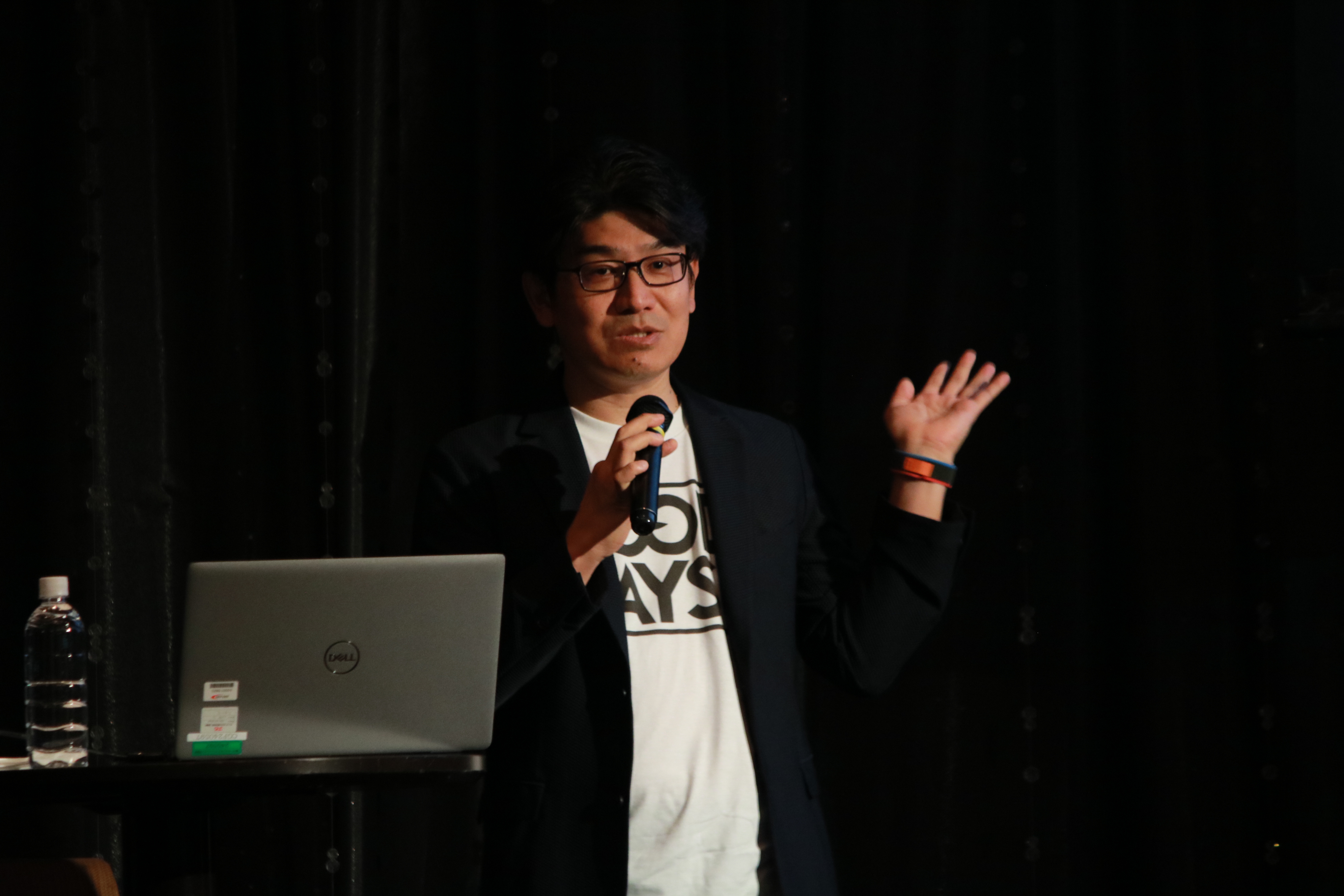
②「CROSS TALK」
「作り手×○○」をテーマに、一次産業や二次産業の「作り手」と、他分野の「創り手」による掛け合わせの可能性についてトークセッションを行いました。3会場に分かれ9つのトークセッションが繰り広げられ、テーマに対するそれぞれの想いを語り合いました。
※各トークのレポートは後述









③「FOOD CREATOR AWARD」
本アワードでは、「育てる」「届ける」「食べる」の各分野で活躍する次世代フードクリエイターたちによる、熱意のこもった5分間のピッチが行われました。
事前選考を通過した6名が、それぞれの事業内容や特徴、今後の展望をプレゼンテーション。この地域を牽引していく未来のつくり手を発掘する、貴重な機会となりました。
大賞を受賞された「JAひまわり 佐藤 光」さんには、ピッチで語られた構想の実現のためにサーラグループが半年間の伴走支援をします。


④「CROSS PARTY」
DAY1の夜を締めくくったのは、立食ブッフェ形式の展示・交流会。
東三河の食材を使用した地域外のプレイヤーと地元企業を合わせた13社と、ホテルアークリッシュ豊橋の料理を合わせた、色とりどりの様々なブッフェ料理が会場に並びました。
出展した企業は、商品の魅力を直接体験・試食してもらう機会となり、参加者同士でも活発な交流が行われました。業種の垣根を超えた連携が生まれるとともに、今後の新たな展開に期待が高まります。


【DAY2】
⑤「CROSS WALK」
山・川・海が存する自然豊かな東三河で、食が生まれる現場をめぐる1日限定のプランを、山・海の2コースに分かれて体験しました。
山コースでは、奥三河を舞台に、米作りから日本酒づくりの過程、その過程で生まれる酒かす・くず米が家畜の飼料となり、家畜から出た堆肥が米作りへと使われる一連の「食の循環」を体験。酒工房、牧場、田んぼを巡り、私たちの食がどのように育まれ、繋がっていくのかを、美味しいステーキと日本酒を味わいながら学びました。
海コースでは、全国トップクラスの農業地域である渥美半島を舞台に、生産物と海の魅力を体感しました。気候に合わせた独自の手法で少量多品目の野菜を育てる生産者や、ナイトツアーを開催して観光地としても人気の電照菊の圃場に訪問しました。
そして、半島の先端に位置する渥美魚市場にて、活きた魚を目の前で捌き、オリジナル海鮮丼をいただく新鮮な食を体験。海の恵みと生産者の情熱を肌で感じました。




⑥「CROSS DINNER」
2日間最後のコンテンツは、3人のシェフによる一夜限りのスペシャルブッフェ。東三河の食材をテーマにこだわり抜かれた料理が並びました。
ブッフェでは、シェフ自らが趣向を凝らした演出料理を披露し、食材を選んだ背景や思いについても語っていただきました。料理を「食べる」だけでなく、その一皿に込められたストーリーに触れることで、食の体験はより豊かで奥深いものに。
また、CROSS WALKからの参加者は、巡った場所の食材やお酒と再会し、その体験が思い起こされ、食材と人、そしてストーリーがつながる特別なひとときとなりました。




来場者の声
・普段はなかなか会うことが出来ない方々の話を聞き、交流が出来たことがとても貴重な体験、刺激になりました
・正直東三河のことはきちんと知らなかったのですが、2日間の充実したプログラムのお陰で深く体験することができました
・他の生産者や事業者と共創の輪を広げる感覚を共有する機会になる良いイベントだと思います
・普段交わることのないシェフと東三河の豊かな食材のコラボを間近で見え、感じることができました
まとめ
2回目の開催となる「東三河FOOD DAYS 2025」は、昨年のイベントで出会った方々に加え、スタートアップや学生、料理人など、昨年以上に様々な地域・立場の皆様にご参加いただき、語らい、繋がる2日間となりました。
今年の大きな特徴は、東三河地域外からの来場者が全体の半数に上ったことです。この地の豊かな魅力、そして「フードクリエイターの聖地」としての可能性を多くの人に肌で感じていただけたのではないでしょうか。今後はこの熱をさらに広げ、「内から外へ」と東三河の魅力を発信していきます。
「東三河FOOD DAYS」は、農と食に関わる人々が交流し、新しいつながりを育む場。
ここで生まれた事業やアイデアを積極的に地域へ還元し、東三河が「フードクリエイターの聖地」になることを目指します。

CROSS TALK レポート
【CROSS TALK 作り手×観光】
「より深い日本を求める外国人観光客が増えている」——そんな言葉から始まった今回のセッション。
中部国際空港が集客に苦戦している現状も踏まえ、今の観光には“体験”としての地域の魅力が求められていると感じました。
中でも「食」は、まだ海外に知られていない価値が多く眠っていて、地域とつながる可能性を秘めています。移動そのものが目的になるような旅のかたち——それ自体がコンテンツになるという視点は今後重要になってくると思います。
また、「点と点をつなぎ、面で売り出していくことが大事」という言葉も印象的でした。
地域資源を個別に発信するだけでなく、流域やエリア全体を舞台にした体験型コンテンツとして展開することで、より立体的に魅力が伝わるはずです。
豊川流域での連携構想には、地域観光の新しい可能性が見えました。
【CROSS TALK 作り手×アトツギ】
遠くは香川市三豊町から、長くは391年の歴史と、バラエティに富んだメンバーが、
「アトツギ」という共通点で集まり、熱く語り合った本トークセッション。
最初のテーマは、「アトツギだからこそ守るべきこと、変えるべきこと」
「守るべきことは信用。それを壊すのは一瞬。」(両口屋是清:大島千世子さん)
「飲食店の働き方は時代に合わせて変えなければならない。」(HTH:馬飼野亮太さん)
どちらの言葉も力強く、アトツギとしての自覚と品格に満ちていました。
次のテーマは、「地域の魅力発信」
地元の中学生への協力や、観光向けのコンテンツの創出など、地元に根差す老舗企業だからこその地域への想いを語っていただきました。
そして最後のテーマは、「リーダーシップとチームワークのバランス」
先頭を走って背中を見せるリーダー、メンバーに任せるリーダー、自分の等身大を見せて助けてもらうリーダー。
アプローチは違いながらも、誰よりも仲間とのコミュニケーションについて考え続けている5人のリーダー像を見ることができました。
「また会いましょうが大事。今日から次に繋がるアクションをしましょう。」(三星グループ:岩田真吾さん)
ユニークなメンバーによる、参加者も一体となったセッションでした。
【CROSS TALK 作り手×アグリテック】
施設園芸が盛んな愛知県。そしてそのうちの75%が東三河で営まれています。
それを支える、ICTやロボット技術を活用した農業「アグリテック」。
このセッションでは、メガサイズで展開するメーカー、先進的な個人生産者(ストロングミニマム)、新技術を提供するスタートアップ、そして教育・研究機関のそれぞれの立場から、アグリテックの現在地と未来への期待が語られました。
一方で、イニシャルコストがかかることや、個人生産者の意識がまだ不十分であるという課題も、実例を持って共有されました。
農業の見える化によって「誰でもできる農業」を実現し、空きハウスでの新規就農、収益化を容易にすることで、地域の人口増に繋げたい、という力強い意欲が感じられました。
施設園芸に限らず、これからの生産現場ではデジタル技術を「使う」ことの重要性を感じるセッションでした。
【CROSS TALK 作り手×料理人】
今回のセッションでは、「日本の食にどんな変化や課題があるのか?」という問いから議論がスタートしました。
物価が上がりづらい日本では、そのしわ寄せが料理人の労働時間に現れているという声や、気候変動による産地の不安定さ、価値の伝え方がまだ十分にできていないという課題が共有されました。
食の現場では、価格以上に“伝え方”や“選び方”が問われているのだと感じました。
続いて、「料理人に求められる役割とは?」というテーマでは、食べ手の育成が重要だという意見が印象的でした。
また、若い世代が料理人という職業を“選択できる”環境づくりも大切だという話もありました。
最後に、「日本の食の未来のために今できること」として挙がったのは、“考えて食べること”。
自分なりの判断基準を持つことが、食の課題解決につながるという言葉が、心に残りました。
【CROSS TALK 作り手×リスキリング】
東三河が「フードクリエイターの聖地」になるにはどうしたらいいのか?
生産者、教育者、料理人、都市のディベロッパーなど、登壇者それぞれの視点を交えながら、「食のリスキリングを通じた全国から人を呼び込むまちづくり」が議論されました。
東三河は農業産出額が高く、食に関する高いポテンシャルを有しています。一方で、30歳未満の労働人口の多くは都市部へ流出しています。
食や地域の可能性は感じられているはずなのに、いざ地域で食の現場に就きたいか、と言われるとそうではないということです。
生産者や料理人、メーカーなど、日々の食卓を守る作り手が、職業として選ばれるようになるにはどうしたらいいのでしょうか。
その解のひとつが、この地に食のリスキリングや人材育成の場が整備されることだと熱く語られました。
スペインバスク地方のように、食に携わる職人の価値を社会的に認めるシステムをつくることで、キャリアの価値が正当化され、なりたい職業になっていく。
「普段は一等星・二等星しか見えていないけど、地域の食は六等星まである。輝いているのに見えていないだけ。だから発掘ではないんです。」(武藤:武藤太郎さん)
既に地域にある価値を見つめなおすことの重要性を感じるセッションでした。
【CROSS TALK 作り手×都市型農業】
今回のセッションでは、「都市農(アーバンファーミング)から都市農業、そして農業へ」という流れをどうつくるかが大きなテーマでした。
この道筋は、まちづくりと密接に関わっていて、農に触れるハードルを下げ、自分ごととして捉えることで、新しい農業のかたちが見えてくる——そんな視点が印象的でした。
また、都市型農業が「生産者・料理人・消費者」をつなぐ役割を果たす可能性についても議論がありました。
ここ30〜50年、食の現場では試行錯誤が止まっていたとも言われ、都市型農業がその停滞を打破するきっかけになるのでは、という期待が語られました。
さらに、「食と農のコミュニティをどう考えるか?」というテーマでは、消費者と生産者の間にある壁を壊すことの重要性が語られました。
料理という行為を通じて農の価値が伝わり、コミュニティが育まれる。そのループを大切にしていきたいです。
問い合わせ先
サーラ不動産株式会社 フードバレーグループ
電話番号:0532-51-5800(月~金 10:00~12:00、13:00~17:00)
メールアドレス:higashimikawa-foodvalley@sala.jp
東三河フードバレーサイトはこちら(https://higashimikawa-foodvalley.jp/)
