~厚生労働省記者クラブにて最新研究成果を発表、持続可能な捕鯨と日本の食文化を再考~
一般社団法人日本捕鯨協会(理事長 谷川 尚哉)は、一般財団法人日本鯨類研究所、共同船舶株式会社の協力のもと、2025年9月25日(木)に厚生労働省記者クラブにて記者発表会を開催し、鯨肉・鯨油の健康増進機能についての最新の研究成果を発表しました。
本発表会には、報道関係者多数が参加。鯨肉・鯨油が持つ健康増進効果について、湘南医療大学 薬学部の塩田清二教授、早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構の矢澤一良先生、共同船舶株式会社 代表取締役社長 所英樹氏、そして一般社団法人日本捕鯨協会 谷川尚哉理事長が登壇し、最新の科学的知見と今後の展望について解説しました。
所社長からは、「持続可能な捕鯨は、日本の食文化を守るだけでなく、水産業全体の未来を切り拓くものです。鯨肉・鯨油の機能性を科学的に証明することで、若い世代にも新しい食の価値を伝え、日本ならではの資源循環型の社会を実現していきたい」と発言がありました。
湘南医療大学 薬学部の塩田清二教授からは、バレニンは抗酸化能が高く、アスリートの臨床試験で持久力向上・自律神経調節・睡眠改善を確認。また高齢者では認知機能や集中力の向上、抗ストレス・抑うつ改善を示したことが紹介されました。さらに鯨油に含まれる多価不飽和脂肪酸(DPA・EPA・DHA)が血中・肝臓の脂肪量を減少させることを報告しました。早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構の矢澤一良先生からは、予防医学、特にオール世代のフレイル対策として、鯨がもつ“マリンビタミン”の有効性についてご講演いただきました。さらに、ヘルスフード科学の立場から鯨の機能性に注目され、特に抗疲労成分イミダペプチド「バレニン」が、ヘルスフードや化粧品素材として有用であることが示されました。

発表のポイント
1.鯨肉に含まれるイミダペプチド「バレニン」の新知見
-
高い抗酸化作用により疲労軽減・持久力向上・自律神経安定・睡眠改善に寄与
-
高齢者での集中力向上・抗ストレス・抑うつ改善を確認
-
高校生アスリート臨床試験で疲労感改善・睡眠質向上・集中力向上を報告
2.鯨油の機能性と生活習慣病予防への可能性
-
DPA・EPA・DHAなどのオメガ3脂肪酸により、中性脂肪・脂肪肝の改善を動物・ヒト試験で確認
-
育毛効果や美肌など、抗酸化を活かした新しい応用可能性も提示
3.鯨資源の持続可能な利用と海洋生態系保全の視点
-
鯨の過剰保護が漁業資源減少やアニサキス増加を招く可能性を指摘
-
科学的管理(RMP・遺伝子トレーサビリティ)により100年先まで資源維持が可能
-
適切な捕鯨が海洋資源の循環活用と生食文化の安全性に寄与
4.「マリンビタミン」によるフレイル予防と予防医学への示唆
-
海洋生物に含まれるビタミン様成分を活用した新しい健康コンセプト
-
鯨肉・鯨油が栄養と機能性の両面からフレイル対策に有効であることを強調
登壇者からのメッセージ
-
一般社団法人日本捕鯨協会 理事長 谷川 尚哉 氏
「鯨食文化は、単なる伝統ではなく、環境・健康・経済に貢献する持続可能な資源活用です。かつて“クジラは食べてはいけない”とされた認識を、科学的エビデンスで覆す時期に来ています。この度は、厚生労働省という場所で、最新の研究成果を発表させていただく機会をいただき、感謝しています。」
「若い世代では鯨を食べる文化は薄らいでいるが、鯨はどんどん食べていい。昔から鯨は高たんぱく、低カロリーで健康に良いといわれてきた。今日は健康に寄与する鯨の最新の研究成果を発信したい」と鯨の食品としての健康増進効果をアピールしました。

鯨の資源管理と海洋環境への影響、そして鯨肉・鯨油の健康機能性について
-
共同船舶株式会社 代表取締役社長 所 英樹 氏
■ 鯨と海の豊かさを守るために
鯨は1日に体重の約4%もの餌を食べます。日本鯨類研究所の試算では、世界の鯨が1年間に食べる水産資源は、人類の年間漁獲量の3~6倍にのぼります。食物連鎖の最上位にある鯨を過剰に保護し続けることは、海洋生態系のバランスを崩し、漁業資源の減少にもつながります。
ここで注目したいのは、鯨は1頭捕獲すれば年間でその体重の約15倍の餌となるサンマやサバ、イワシなどの水産資源が人類のために利用可能になるという点です。つまり、適切な捕鯨は海洋資源をより多くの人々が利用できる持続可能な取り組みなのです。
私たちの捕鯨は、国際的に認められた改訂管理方式(RMP)に基づき、100年先まで健全な資源状態が維持されるよう科学的に管理されています。さらに、流通段階では個体ごとの遺伝子登録によるトレーサビリティが徹底されており、安心・安全な食料資源として提供されています。
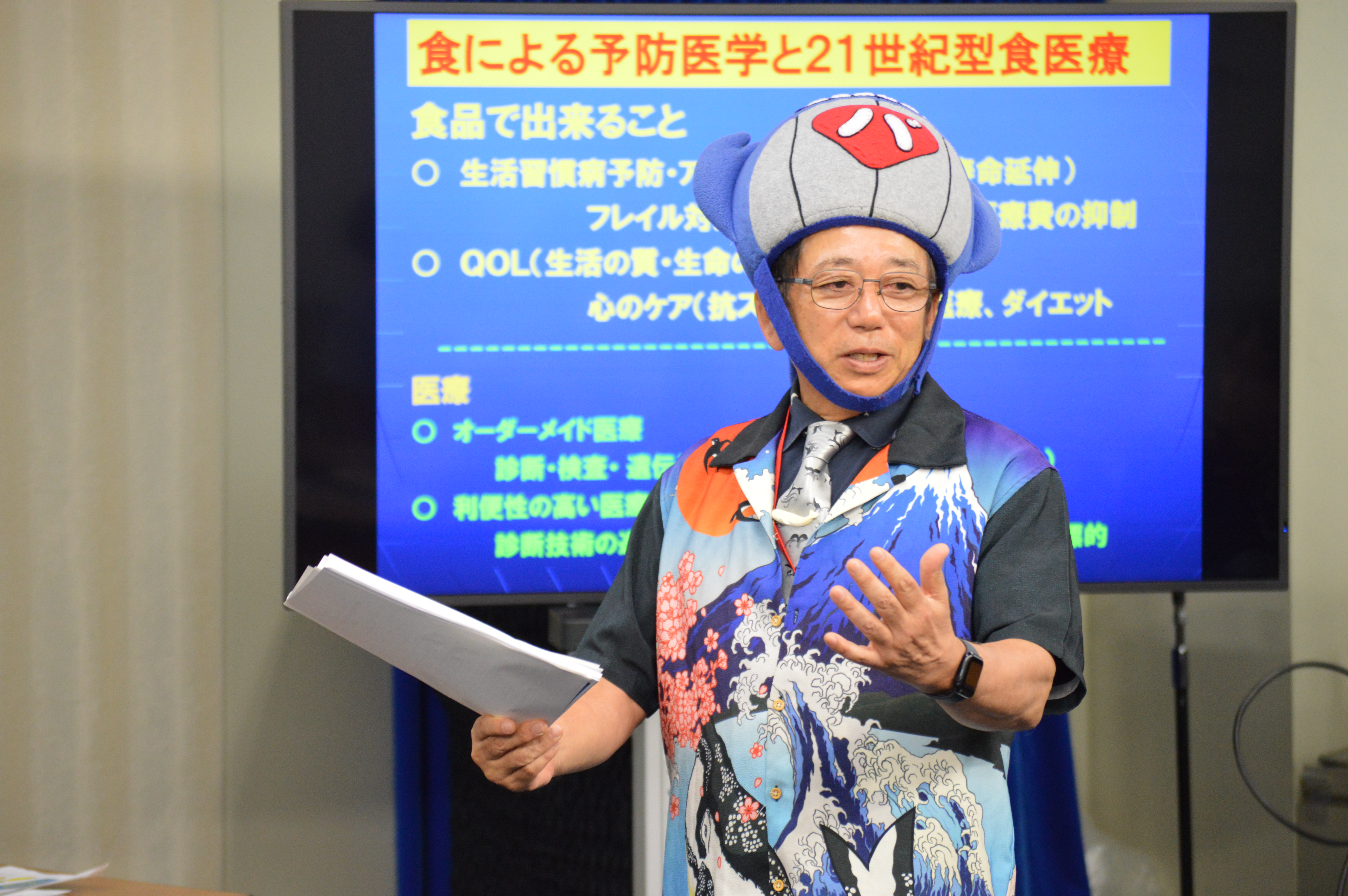
■ クジラとアニサキスの関係
近年、魚介類によるアニサキス症が注目されていますが、鯨肉から感染することはありません。アニサキスは鯨やイルカを最終宿主としており、卵は鯨の体内でしか成長できません。つまり、鯨が増えるとアニサキスも増えます。適切な捕鯨は、漁業資源だけでなく、生魚を安全に食べる文化を守る上でも重要です。
■ 高校生アスリートとバレニンの力
鯨肉に多く含まれるイミダペプチド「バレニン」には、抗酸化作用があり、疲労軽減や持久力の維持に効果が期待されています。今回、野球やラグビーなどに取り組む全国13校・350名の高校生に4週間バレニンサプリを摂取してもらったところ、
-
疲労感が改善(58.1%がポジティブ変化)
-
睡眠の質が向上(55.9%)
-
集中力も向上(54.2%)
といった結果が得られました。
良質な睡眠が筋力や体力の回復を助け、パフォーマンス向上につながることも示されています。ただし摂取をやめると集中力が低下する傾向が見られ、継続摂取が重要であることも分かりました。
鯨を適切に利用することは、海洋資源の保全と有効活用、生食文化の安全確保、健康・スポーツ分野の発展につながります。私たちは今後も科学的根拠に基づき、鯨資源の持続可能な利用と、鯨由来成分のさらなる健康効果の研究を進めてまいります。
鯨肉及び鯨油についての動物実験およびヒトにおける臨床研究について
-
湘南医療大学 薬学部 教授 塩田 清二 氏
■ バレニンの特徴と効果
まず、鯨肉にはイミダペプチド「バレニン」が豊富に含まれています。
バレニンは、魚類や鳥類にも少し含まれていますが、鯨肉はその含有量が非常に高いのが特徴です。バレニンには強い抗酸化作用があり、動物実験では疲労を軽減し持久力を高める効果が確認されています。
近年、私たちはアスリートを対象とした臨床試験を行い、バレニンを摂取した選手たちで
-
持久力の向上
-
自律神経の安定
-
睡眠の質の改善
といった効果を確認しました。運動とバレニンを組み合わせることで、より高い健康増進効果が期待できると考えています。
■ 筋肉とマイオカインへの影響
さらに、筋肉が収縮するときに分泌されるマイオカインという物質に注目しています。これは、筋肉から分泌されるホルモン様の物質で、全身の健康に深く関わっています。私たちは、運動している筋肉の培養細胞にバレニンを加えた実験を行い、健康維持に重要とされる複数のマイオカインの発現が増えることを見つけました。
また、増加したマイオカインで検証した結果、同じイミダペプチドであるカルノシンやアンセリンよりも、バレニンのほうが高い発現効果を示すことも確認しています。
■ 認知機能・ストレス・長寿への作用
バレニンは脳機能やストレスにも良い影響を示しています。これまでの研究で、認知症モデルマウスではバレニン摂取によって認知機能が改善されました。
高齢者を対象にした臨床試験でも、バレニンを摂取した方はプラセボ群よりも集中力や作業効率が高く、ストレスや抑うつ感が和らぐことが分かりました。
さらに、最近の線虫を使った実験では、バレニンを含む餌を与えたところ、
-
寿命が延びる
-
運動機能が向上する
-
長寿遺伝子の発現が高まる
といった結果が得られました。
成人男性でも、バレニン摂取によって長寿遺伝子Sirt1の発現が上がることを確認しています。
■ 鯨油に含まれるオメガ3脂肪酸の効果
次に、鯨油についてです。
鯨油にはDPA・DHA・EPAなどのオメガ3脂肪酸が豊富に含まれており、記憶力の向上、生活習慣病の予防改善、筋肉痛の軽減などさまざまな効果が知られています。
私たちの動物実験では、鯨油を含む餌を肥満マウスに10週間与えると、
-
血中の中性脂肪が減少
-
肝臓の中性脂肪やコレステロールも減少
-
脂質合成に関わる遺伝子(FAS)の発現が下がる
ことが分かりました。
ヒトを対象とした臨床試験でも、鯨油カプセルを3カ月摂取すると血中中性脂肪が顕著に低下する結果が得られています。
■ 意外な効果 ― 鯨油と育毛
さらに興味深いことに、オメガ3脂肪酸の高い抗酸化作用に注目して育毛への影響を調べたところ、
-
培養したヒト毛乳頭細胞で増殖効果がみられ、
-
マウスの皮膚への塗布実験では、コントロールや既存の育毛剤よりも高い育毛効果
が確認されました。

これらの研究結果から、鯨肉や鯨油には生活習慣病リスクの改善、筋力や持久力の向上、脳機能の活性化など、さまざまな健康増進作用があることが明らかになってきました。
今後は、鯨由来成分が持つまだ解明されていない効果についてもさらに研究を進め、人々の健康寿命の延伸に貢献したいと考えています。
鯨から期待されるマリンビタミンについて
-
早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 矢澤 一良 氏
■ マリンビタミンとは何か
「マリンビタミン」とは私が考えた造語です。ビタミンAやCのような特定の栄養素ではなく、海洋生物が持つ“ビタミンのように生理活性の高い機能性成分”を総称したものです。
日本は古くから魚介類や海藻を日々の食卓に取り入れ、自然の恵みであるマリンビタミンを摂取してきました。その結果、戦後には世界一の長寿国となり、穏やかな性格や高い知能、女性のきめ細かな肌などが世界から評価されるようになったと考えています。
■ 現代の課題:フレイルと生活習慣病
しかし近年は食生活が欧米化し、かつての鯨食文化も薄れたことで、生活習慣病やフレイル(加齢による心身の虚弱)が急増しています。
フレイルは高齢者だけでなく、若年層の偏った食生活やストレスによっても進み、筋力低下・免疫低下・脳疲労などの“フレイルスパイラル”を引き起こします。
予防には、栄養バランスの取れた食と日常的な運動が不可欠です。
■ 鯨のマリンビタミン ― バレニンの力
その中で注目すべきが鯨に豊富に含まれるイミダペプチド「バレニン」です。
バレニンは筋肉の中に長時間とどまり、強い抗酸化作用でミトコンドリアを保護し、疲労軽減・持久力向上・自律神経の安定・睡眠の質向上など多彩な健康効果が期待されています。
さらに、マイオカインという筋肉から分泌される物質を増やし、筋肉や免疫、脳機能にも良い影響をもたらすことが研究から分かってきました。
■ 海の恵みと予防医学
鯨肉には、バレニンのほかにもEPA・DPA・DHAなどのオメガ3脂肪酸、ミネラル、コラーゲン、コンドロイチンなど多彩な栄養素が含まれています。
これらは血流改善・認知機能の維持・骨や関節の健康・アンチエイジングなどに寄与します。
こうした海の恵みを活用することは、まさに“食による予防医学”の実践であり、健康寿命の延伸や医療費抑制にもつながります。
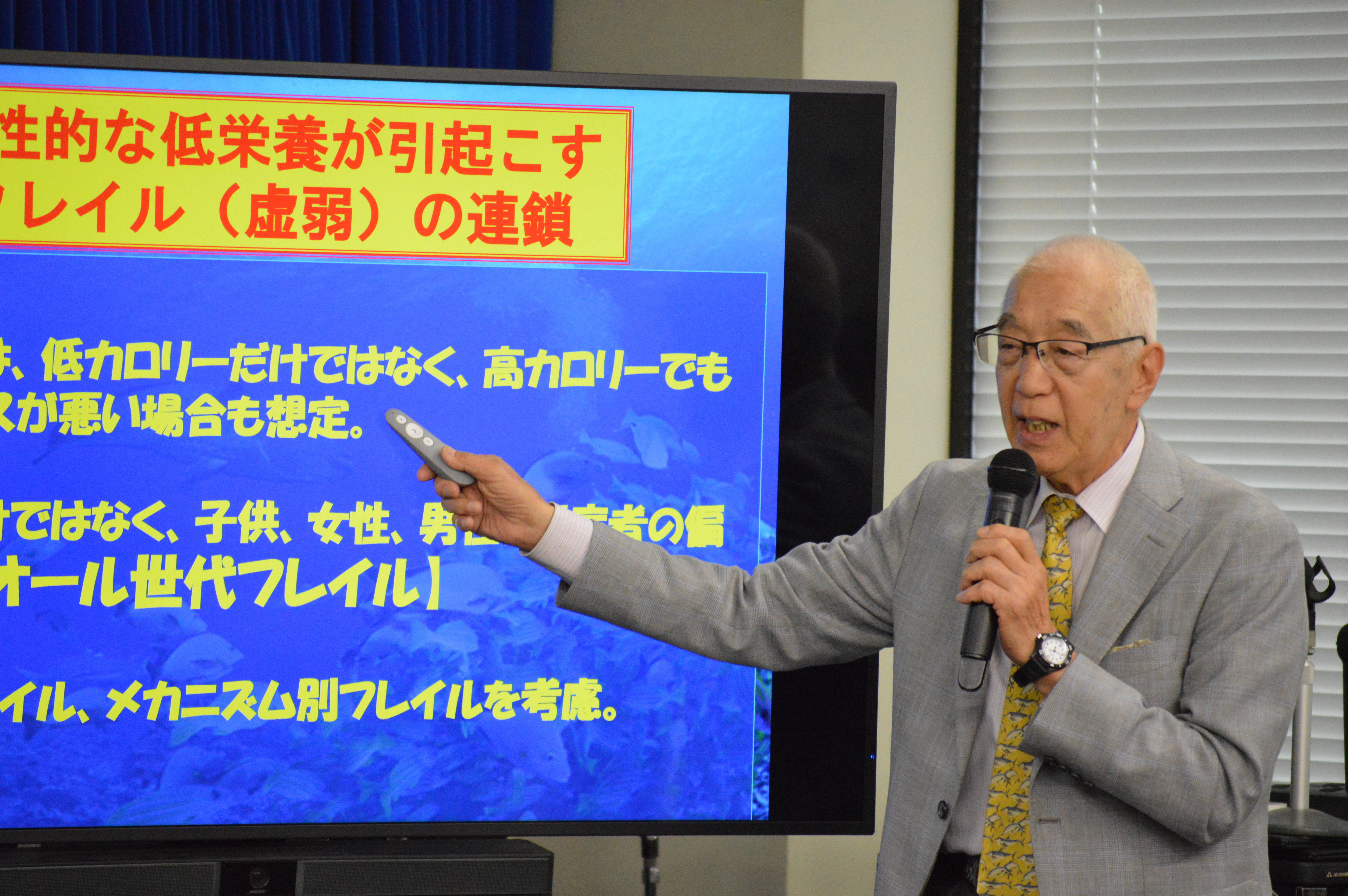
私たち研究者の使命は、伝統的な食材に潜む機能性を科学的に解明し、現代の生活習慣病やフレイルといった課題の解決に役立てることです。
鯨をはじめとするマリンビタミンの力を活用し、健康とQOL(生活の質)を高める未来をつくっていきたいと考えています。
開催概要
主催:一般社団法人日本捕鯨協会
協力:一般財団法人日本鯨類研究所、共同船舶株式会社
タイトル:「鯨の健康増進機能の新たな発見・最新研究成果 ~遺伝子レベルでフレイル予防~」
日 時: 2025年9月25日(木)13:00~14:00
会 場: 厚生労働省 記者クラブ内「会見室」
登壇者:
一般社団法人日本捕鯨協会 理事長 谷川 尚哉
共同船舶株式会社 代表取締役社長 所 英樹
湘南医療大学 薬学部 教授 塩田 清二
早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構 矢澤 一良
