〜農林水産大臣賞受賞プログラムが、東京・京都から日本の水産資源と食文化の未来を担う人材を育成〜
豊かな海と食文化を未来につなぐため、国内トップシェフら約40名と共に活動する一般社団法人Chefs for the Blue(本社:渋谷区千駄ヶ谷/代表理事:佐々木ひろこ)は、2025年9月1日(月)より、トップシェフの伴走のもと、学生が漁船に乗るフィールドワークから期間限定レストランの企画・運営までを駆け抜ける実践型教育プログラム『ブルー キャンプ 2025』の学生募集を開始いたします。「ブルーキャンプ」は2023年からはじまり、今年で3回目の開催になります。
「ブルーキャンプ 2025」HP:https://thebluecamp.jp/
応募フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem37vjt9Fym-FIu7-HKc2IJIGsyvfhhoS7Gn6DbuMnyU7tmQ/viewform

なぜ、トップシェフが厨房を飛び出すのか?
―日本の海が直面する“静かなる危機”と、未来への人材育成
日本は海に囲まれた島国という立地から、古くより魚介を使った料理が豊富で、世界でも有数の洗練された魚食文化を築いてきました。一方で、2023年の漁業・養殖業生産量は383万トン(※1)と、ピークだった1984年の1,282万トン(※2)と比べて1/3以下に落ち込んでいます。私たちの食文化の根幹をなす魚が、このままでは食卓から消えてしまいかねない状況です。
国土開発や遠洋漁業の衰退、温暖化による海洋環境の変化などさまざまな要因があるなか、魚が減った大きな理由として長年指摘されてきたのが過剰漁獲です。その解決を目指した水産改革が2018年にはじまり、現在国による資源管理の取り組みが進められていますが、残念ながらまだその成果は出ておらず、 漁獲量は減少を続けています。
Chefs for the Blueは日本の食文化醸成を担うトップシェフチームとして、この海の課題に2017年から全力で向き合ってきました。漁業現場を真に変え、海の豊かさを取り戻し、食文化を未来につなぐためには、改革のさらなる推進はもちろん、複雑に絡み合ったサプライチェーン全体の変容も必要だと考えています。そしてそのためには、業界横断で活躍できる未来のチェンジメーカーの存在が不可欠です。ブルーキャンプは5ヶ月間の徹底した学びを通じて海や水産業の現状と食文化のすばらしさを見つめ、課題解決の視点と企画力を養い、トップシェフの徹底伴走のもと、社会にメッセージを届けるシーフードレストランを各チーム8人で作り上げる実践型プログラムです。多様な学問領域から集まる学生たちとともに、今年も5ヶ月を走り抜き、未来の海を支えるチェンジメーカーを育てることを目指します。多くの学生のご応募をお待ちするとともに、本プログラムの活動をメディアの皆様にも随時公開してまいります。
注釈:
※1:令和6年度版『水産白書』
※2:農林水産省統計部「漁業・養殖業生産統計」


<過去2回の開催を経て、今年で3回目へ。卒業生は食の未来を担う現場へ>
これまで2023年、2024年に開催してきた「ブルーキャンプ」では、全国から集まった学生たちが海と食が直面する課題と向き合ってきました。現場のリアルと葛藤を体験し、伝えるべき課題や「未来につなげたい」食のありようについて議論し、考え抜いた日々の集大成として、6日間のシーフードレストランを運営してきました。
2年間で約500名のゲストをお迎えしたこのレストランは、ただ美味しい料理を提供するだけの場ではありません。「食用マイワシは漁獲の20%」「真昆布の枯渇危機」「魚網の目合で獲れる魚は変わる?」といった、社会に知られていない(でも知れば興味深い)水産現場の現状を美味しい料理を通して伝えたり、「未利用魚の可能性」「クロマグロの資源回復」といった「希望」を語りかけたりするなかで、ゲストの心を強く動かしたシーンが数多くありました。
参加した学生からは、「海の課題が初めて自分自身の問題だと感じられた」「海のことを知る人が増えれば未来はきっと変えられる」という声が上がっています。「おいしい」という感動を入り口に、海の課題を”自分ごと”化し自ら動く。プログラム終了後、学生たちは英Economist主催の国際会議「World Ocean Summit」」における島嶼国や国際機関首脳向けのディナープログラムや、大阪万博「ブルーオーシャンドーム」におけるイベント運営など、幅広く活躍しています。ブルーキャンプは、次代を担う若者たちの心に火を灯し、社会に新しい視点を提示する変革の舞台となっているのです。


<ブルーキャンプについて>
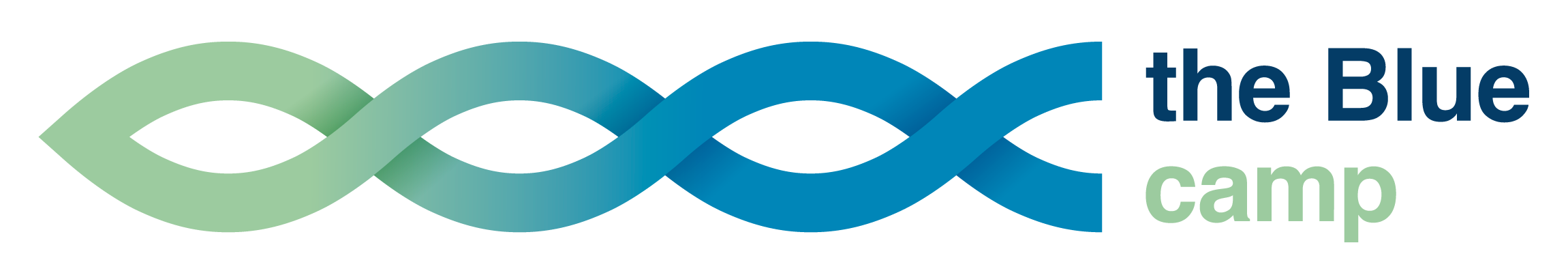
ブルーキャンプは、持続可能な未来を担う次世代育成を目的に、2023年に始まった海と食の教育プログラムです。全国から選抜された16名(東京・京都各8名)の大学生・専門学生が座学、フィールドワーク、レストラン研修を通して海と食について学び、5ヶ月間の集大成として、社会にメッセージを伝えるためのシーフードレストランを6日間運営します。Chefs for the Blueが関係性を培ってきた産官学のトッププレイヤー陣から学べることが特長で、レストランづくりでは日本を代表するシェフ達4名が徹底伴走します。
note:https://note.com/the_bluecamp/
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=HeIKjMraCMw
「ブルーキャンプ」3つの特徴
①農林水産大臣賞受賞の教育プログラム
第一線の学びに連なる本格的な実践、多様なバックグラウンドを持つ学生の協働が評価され、「サステナアワード2024」にて農林水産大臣賞を受賞しました 。
②トップシェフが徹底伴走
ミシュラン星付きレストランのシェフを含む4名がメンターとして徹底的に伴走。調理技術だけでなく、レストランでの「メッセージの伝え方」や哲学を直接伝えます 。
③水産サプライチェーンを貫く学び
漁業者から水産庁職員、流通のプロ、研究者まで、業界のトップランナーが講師として集結。サプライチェーン全体の視点から、複雑な海洋課題を構造的に理解する機会を提供します。
<「ブルーキャンプ 2025」詳細>
約5ヶ月間にわたり、海と食の未来を多角的に学ぶ座学から実践までのカリキュラムで構成されています。プログラム実施期間:2025年11月9日(日) ~ 2026年3月16日(日)まで
1. キックオフ/合宿
参加者およびシェフ、またプログラム全体に伴走するコーディネーターの顔合わせ。オンラインでのオリエンテーション、そして静岡県で行う漁港フィールドワークを含む合宿がキックオフとなります。
11月9日(日)20:00-22:00: オンライン始業式
11月15日(土)- 16日(日): フィールドワーク合宿(静岡県伊東市)
訪問先: 城ヶ崎海岸富戸定置網、伊東漁業協同組合(市場)など
講座: ②「資源としての魚/資源管理」③「メディアとしてのレストラン」
2. オンライン講座
海と漁業について、持続可能性と資源管理について、食文化についてオンラインで学びます(zoom使用/講座②のみオンサイト)。講座は各2時間、東京・京都共通の内容となります。
11月12日(水): 講座① 食材としての魚/魚と食文化(講師:佐々木 ひろこ)
11月19日(水): 講座④ 生物としての魚/魚と環境(講師:清野 聡子氏)
11月26日(水): 講座⑤ 商材としての魚/魚と流通(講師:山本 徹氏)
12月3日(水): 講座⑥ 「伝える」とは(講師:高木 新平氏)
※講座②、③は合宿内で実施します。
3. 産地フィールドワーク
自然と向き合う水産業の現場に立ち合い、水揚げやセリの見学、漁業者や仲買人との対話を通じて、水産物生産・流通の理解を深めます。さらに沿岸漁業にとって重要な、森川里海の連環を学ぶためのサイトも訪問します。
・東京チーム
日時: 11月24日(月)
場所: 神奈川県横須賀市、三浦市、葉山市
訪問先: 長井漁港(「さかな人」)、葉山アマモ協議会、小網代の森など
・京都チーム
日時: 11月30日(日)
場所: 京都府舞鶴市、宮津市
訪問先:京都大学舞鶴水産実験所、京都府漁業協同組合 舞鶴市場、 飯尾醸造など
4. レストラン研修
東京と京都、それぞれでトップクラスの人気と実力を誇るレストランのキッチンやダイニングルームで、レストランや料理についての学びを深め、メニューやサービス、店づくりの内容を考えます。作り手(生産者)と食べ手(消費者)の両方と繋がるレストランという場所で、実践的な学びを得ます。
東京チーム: 12月6日(土)ランチタイム @メログラーノ(シェフ:後藤 祐司氏)
京都チーム: 12月6日(土)ランチタイム @モトイ(シェフ:前田 元氏)
5. 企画会議
ポップレストラン営業成功に向けて、コーディネーターと共に企画会議を進めます。チーム各人の得意分野を活かしながら、どうすれば海と食の課題を伝え、理想の未来を示すことができるのか議論を深めていきます。
対面会議: 東京 12月13日(土)、20日(土)/ 京都 12月7日(日)、20日(土)
オンライン会議: 2026年1月14日(水)~3月4日(水)の毎週水曜日
6. ポップアップレストラン
学生チームだけでシーフードレストランを企画し、春休み期間中に6日間ポップアップ営業を行います。どんなレストランを作りたいのか、どんな魚介類を使った料理にするのか、スタッフの配置は、メニュー構成は、お客さまとのコミュニケーションはなど、企画期間、営業期間をとおしてシェフおよびコーディネーターがメンターとして伴走しながらサポートします。
<東京チーム>
期間: 2026年3月10日(火)~ 3月16日(月)
場所: 日本食品総合研究所(東京都渋谷区代官山町)
<京都チーム>
期間: 2026年3月9日(月)~ 3月15日(日)
場所: コミュニティキッチンDAIDOKORO(京都市中京区 QUESTION8F)
※日程や訪問先は、状況により変更となる可能性がございます。
【2025年メンターシェフについて】
<東京チーム>
東京都目黒区【クラフタル】シェフ 大土橋 真也

1984年、鹿児島生まれ。調理師専門学校のフランス校へ進学し、帰国後は東京・恵比寿のシャトーレストラン【ジョエル・ロブション】などで修業を重ねる。その後再びフランスへ渡り、パリの自然派ネオビストロ【サチュルヌ】で研鑽を積む。2013年に帰国し、東京・初台【レストラン アニス】を経て、2015年9月に同・中目黒【クラフタル】のシェフに就任。さまざまな生産者を日本各地に訪ね、そのストーリーを料理として昇華し創造性豊かに皿上に紡ぐ。2018年よりミシュラン一つ星。
東京都渋谷区【メログラーノ】オーナーシェフ 後藤 祐司

1979年、千葉県生まれ。父親がスパゲティ店を営んでいたこともあり、もともとイタリア料理に親しみを感じていたことからシェフを志す。調理師専門学校卒業後、【クローチェ エ デリツィア】等の名店で修業し、2007年より3年間、シチリア州のミシュランガイド2つ星店【リストランテ・ドゥオーモ】等で活躍する。帰国後の2011年より【ビッフィテアトロ】で4年半シェフを務め、2015年、東京・広尾に【メログラーノ】をオープン。2025年4月に、同じ広尾の地に拡大移転。
<京都チーム>
京都市中京区【レストランモトイ】シェフ 前田 元

1976年京都市生まれ。旧京都グランドホテルの中国料理部門で修業をスタートし、広く料理の基礎を学び、後にホテル日航東京では料理の楽しさを学ぶ。その後フランス料理の料理人になる夢を叶えるために渡仏し、【ラ・マドレーヌ】(ブルゴーニュ地方・サンス)などで修業。帰国後は、京都ホテルオークラや大阪の【HAJIME】で研鑚を積む。2012年に独立し、京都に【MOTOÏ(モトイ)】をオープン。志ある生産者との関係構築はもちろん、スタッフのチームワークづくりや労働環境整備も含めた、総合的なレストランのサステナビリティ向上に取り組む。
京都市上京区【ドロワ】オーナーシェフ森永 宣行

Droit オーナーシェフ 1982年佐賀県生まれ、大阪で育つ。 大学卒業後、フランス料理の世界へ。大阪、京都のレストランで修行。卸売市場の鮮魚店を経て、京都のフランス料理店で料理長を3年半務める。2017年に京都御 所前で「Droit」を開業。2018年より6年連続ミシュランガイド一つ星を獲得。ゴ・エ・ミヨに5 年連続掲載。【ニュージーランド・オーラキングサーモン社】アンバサダー【Chefs for the Blue 京都】チームメンバー【クラブ·ドゥ·レリタージュ·キュリネール·フランセ】理事 。2023年 第20回 メートル・キュイジニエ・ド・フランス“ジャン・シリンジャー杯 準優勝
【講師・メンター陣】 ※敬称略、五十音順
<東京・京都 共通>
・水産庁 資源管理部 管理調整課 資源管理推進室長 赤塚 祐史朗
・水産庁 資源管理部 管理調整課 資源管理推進室 課長補佐 加納篤
・フードジャーナリスト 君島 佐和子
・Chefs for the Blue 佐々木 ひろこ
・九州大学大学院 工学研究院 環境社会部門 准教授 清野 聡子
・NEWPEACE Inc. 高木 新平
・城ヶ崎海岸富戸定置網(株)代表取締役 日吉 直人
・Chefs for the Blue 本間 勇輝
・東京海洋大学 海洋生命科学部 准教授 松井 隆宏
・株式会社フーディソン 山本 徹
<東京>
・Crops -Food x ESD Design- 須賀 智子
・白鷹丸 漁師 仲地 慶祐
・さかな人 長谷川 大樹
・葉山アマモ協議会 副代表 山木 克則
<京都>
・京都大学 舞鶴水産実験所
・富士酢醸造元 飯尾醸造 五代目当主 飯尾 彰浩
・コミュニティキッチンDAIDOKORO 前原 祐作
・漁師 村上 純矢
【募集要項】
<応募要件>
下記条件を満たす方。
①大学生、専門学校生が対象。学んでいる領域は問いません。学校に通っていない若者(この場合、応募締切の9/28時点で20歳以下)も応募可能です。
②海と食の問題を考え、行動することで日本を変えることに興味がある。
③プログラムの全回に出席できる。(学校行事他、どうしても不可能な日については、必ず応募時にご相談ください)
④様々な領域を学ぶ仲間とチームを組み、互いに意見を交わしリスペクトしあいながら5ヶ月間走り抜く意思がある。
⑤食いしん坊である。(グルメである必要はありません)
<参加費>
無料
※各プログラム実施場所までの交通費(漁港視察は集合・解散場所まで)は参加者のご負
となります。
※本プログラムは、日本財団「海と日本プロジェクト2025」のサポートをいただいています。
東京・京都で最大8名ずつという限られた人数になりますが、海の学びとトップシェフのサポートによるポップアップレストラン運営というエキサイティングな体験を楽しんでください。
<応募方法>
応募フォームより、必要情報とあわせて、「わたしと海。わたしと食。」ついての
エッセイ(1000文字以内)を提出してください。
応募フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem37vjt9Fym-FIu7-HKc2IJIGsyvfhhoS7Gn6DbuMnyU7tmQ/viewform
<選考スケジュール>
①9/1 – 9/28 24:00 応募受付
②9/5 – 9/7 オンライン募集説明会
③9.29 -10.19 オンライン面談
④10/24 参加者決定
<今回の取り組みに関するコメント>
一般社団法人Chefs for the Blue 代表理事 佐々木ひろこ

島国に生きる私たちにとって、海の恵みは食文化の根幹をなすものです。しかし、その大切な水産物が40年にわたり海から減り続けているという事実を、多くの人は知りません。海と食への意識を高め、この静かに進む深刻な危機を乗り越え、社会の仕組みを大きく変えていくには、未来を担う世代との連携が不可欠です。そういった想いから2023年、「ブルーキャンプ」をスタートさせました。
このプログラムは、日本水産業が転機を迎えているなか、まだ答えが提示されていない問いに食を通じて向き合う最前線のチャレンジです。過去2回の開催では、学生たちが仲間と時にぶつかり、議論し、悩み抜いた末、一皿一皿に希望や葛藤のメッセージを乗せて、全力でレストランのゲストに届ける姿を見てきました。その経験こそが、今後複雑な問題を多角的に捉え、多様なステークホルダーと協働し、社会を動かす原動力になると信じています。
「おいしい」という感動は、時にどんな言葉よりも強く、人の心を動かします。食いしん坊であることと、社会をより良くしたいという情熱。それさえあれば、経験は問いません。海と食の未来をともに描く仲間となる、皆さんの挑戦をお待ちしています。
<一般社団法人Chefs for the Blueについて>

Chefs for the Blue (シェフス フォー ザ ブルー) は2017年5月、日本の水産資源の現状に危機感を抱いたフードジャーナリストの声がけに応え、東京のトップシェフ約30名が集まった海についての深夜勉強会を起点とする料理人チームです。2021年9月には京都チームも発足。「日本の豊かな海を取り戻し、食文化を未来につなぐ」ことを目指し、NGOや研究者、政府機関などから学びを得ながら、持続可能な海を目指す自治体・企業との協働プロジェクトや各種ダイニングイベント、海の未来を担う次世代の教育事業、飲食業界を中心とした海の学びのためのコミュニティ運営、国への政策提言など、様々な活動を行っています。
【概要】
・法人名:一般社団法人Chefs for the Blue (シェフス フォー ザ ブルー)
・設立日:2018年6月6日 コックさんの日(活動開始は2017年)
・住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-13東急アパートメントB1
・代表理事:佐々木ひろこ フードジャーナリスト
・理事: 【カンテサンス】 オーナーシェフ 岸田周三
【シンシア】オーナーシェフ 石井真介
【ノーコード】オーナーシェフ 米澤文雄
【チェンチ】オーナーシェフ 坂本健
「シーフードレガシー 」代表取締役社長 花岡和佳男
・相談役:【菊乃井】主人 村田吉弘
公式HP:https://chefsfortheblue.jp/
日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。公式HP:https://uminohi.jp/
